航空機には、自動車のナンバープレートのような固有の「機体記号」が表記されています。 自動車のようなプレートではなく、機体に直接ペイントされています。(最近はステッカーが主流のようです。)
機体記号の大きさ、色、表記位置、等々は、航空法施行規則という省令で細かく規定されています。
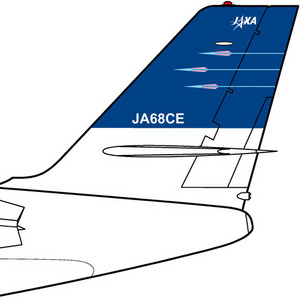
機体記号は、国籍記号+登録記号という構成になっています。この構成は世界共通です。
ただし、構成のうち何桁(何文字)が国籍記号で、何桁が登録記号かは国によって違います。
日本の場合、最初の2桁が国籍記号、そのあとの4桁が登録記号です。
アメリカの機体番号では、国籍記号は1桁で、登録記号は最大5桁となります。
国籍記号のJAは日本国籍を意味します。アメリカ国籍はNで表されます。
 先日、晴れて日本国籍となった「飛翔」。
先日、晴れて日本国籍となった「飛翔」。
機体記号は、「JA68CE」を希望して、希望通りの登録となりました。
「飛翔」の母機がCessna Model 680 Citation Sovereignなので、"68"はモデル680から取りました。
"CE"は、Cessnaの頭文字です。
Cessna 680なので、CE68の方がいいのでは?と思われる方もいるかも知れません。
実は、自由に選べる登録記号にも少しだけルールがあります。
http://www.mlit.go.jp/common/000110612.pdf
- ローマ字については、「I」、「O」、「S」、「CC」、「JA」を含むものは使用できない。
- 使用可能パターンは、数字を○、ローマ字を△とすると、JA○○○△もしくは、JA○○△△の2パターンに限る。
ということで、アルファベットはうしろになります。
また機体番号を決めるときは、無線通信するときの、番号の発音のしやすさも考慮に入れています。
他の実験機たちの機体記号を見てみましょう。
ボナンザ 「JA36AK」
過去のレポート(https://www.aero.jaxa.jp/exair-report/2007/09/27/233000.html)でもふれていますが、36は、母機のビーチクラフト式A36型からきています。AKは、アメリカ、アラスカ州の略称です。
なぜアラスカかといいますと、過去のレポートにあるように、アラスカでおこなったCAPSTONE飛行実験がきっかけで導入された機体だからです。
MuPAL-ε 「JA21ME」
この機体は、西暦2000年に導入されました。
21世紀にはばたくMuPAL-ε、という意味で、21世紀の"21"、MuPALの"M"、εの"E"の組み合わせでできています。
MuPAL-α 「JA8858」
MuPAL-αがこの番号になったのは1988年のことですが、この時代の機体記号は、登録順で割り振られていました。
クイーンエア 「JA5111」
過去のレポート(https://www.aero.jaxa.jp/exair-report/2011/10/28/233000.html)でふれています。
MuPAL-αと同様に登録順で割り振られましたが、かつては、JAのうしろは今のようなローマ字を含む登録記号ではなく、数字のみの4桁の登録番号でした。その中でも、JAのすぐうしろの1桁目(クイーンエアでは5)は、その航空機の種別によって決められた数字でした。
また、表記位置はこのように指示されています。
固定翼機(飛行機)の場合、主翼面(右翼の上面と、左翼の下面)と、尾翼面もしくは胴体面。
回転翼機(ヘリコプター)の場合、胴体の底面と、胴体側面。
 クイーンエア(JA5111)右翼上面(高度23000フィートでの大気観測)。
クイーンエア(JA5111)右翼上面(高度23000フィートでの大気観測)。
 MuPAL-ε(JA21ME)胴体側面。尾翼にみえますが、回転翼機の場合、ここも胴体側面と呼ばれるそうです。
MuPAL-ε(JA21ME)胴体側面。尾翼にみえますが、回転翼機の場合、ここも胴体側面と呼ばれるそうです。
登録記号の288は母機のシリアル番号から(288番目に作られた機体)、JAはおそらく日本にちなんで、ということだと思います。
さらに、このN288JA、エンジンカウル(エンジンの覆い)に書かれていることにお気付きでしょうか。
日本ではエンジンカウルに書かれることはありません。アメリカと日本とでは、表記位置も違っています。
このように機体記号は、国によって、ルールや桁数が異なります。
調べてみると、いろいろ興味深い発見があるかもしれません。

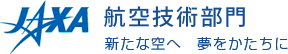








[このページを共有]