ボナンザ機がいよいよJAXAにやって来ました。
この機体は、CAPSTONEでの飛行試験(2006年7~10月のレポート参照)で使用したものです。その後分解されて船で日本に輸送され、今年の3月から調布飛行場内で組み立て、整備作業を行っていました。アメリカから到着して直接調布飛行場に運んだので、JAXAに来るのは本日が初めてです。

調布飛行場からJAXAの敷地に入る瞬間です。

ボナンザは小さくて軽いので、2~3人で押せば動かすことができます(アラスカでも人力でプッシュバックしていましたね)。最後は手で押してハンガーに入れました。

ハンガーに入ったボナンザ。奥にはMuPAL-αが見えます。MuPAL-αの弟分の誕生?
MuPAL-αが調布に戻ってきました。
MuPAL-αは耐空証明検査および改造のため、6月1日から仙台の整備工場へ入っていました。約3ヶ月ぶりの調布です。朝9:35に仙台空港を離陸、10:40に調布飛行場へ到着しました。

ハンガーに戻ったMuPAL-α。ドアというドアが全部開いていました。
 先週、調布へ帰って来たMuPAL-εですが、今度は三陸へ向けて出発です。
先週、調布へ帰って来たMuPAL-εですが、今度は三陸へ向けて出発です。
今回のミッションは、三陸大気球観測所での気球回収支援です。この三陸での支援ミッションは、2004年5月、2005年5月、2006年8月、2007年5月に次いで今回で5回目となります(2005年8月にはクイーンエアも参加)。

MuPAL-εは10:35に調布を離陸、花巻空港を経由して、15:00に観測所に到着しました。予定では、9月9日まで気球回収支援にあたることになっています。
非精密進入と精密進入
2007年7月5日の実験用航空機レポートで計器飛行方式(IFR)と有視界飛行方式(VFR)についてご説明しました。今回は非精密進入と精密進入についてご紹介します。
両者とも、IFRによって空港やヘリポートに着陸する際に航空機を誘導する方式ですが、非精密進入は左右方向のみ誘導を行うのに対し、精密進入は上下(高度)方向の誘導も行います。精密進入の方が、雲が低かったり、視程が悪い条件でも着陸することが可能になるため、就航率が向上します。
非精密進入は、地上に設置されている無線標識(VOR等)を使って行いますが、精密進入を行うためには、これに加えて空港に計器着陸システム(ILS)等の設備を設置する必要があります。風向きに依らずに精密進入を行うためには、ILSを滑走路の両側に設置する必要があり、また複数の滑走路がある空港では、滑走路ごとに設置する必要があります。
 ILSの例です。左右方向、上下方向の誘導を行うシステムをそれぞれローカライザ(LLZ)、グライドスロープ(GS)と呼びます。LLZは滑走路の延長線上に、GSは滑走路の脇に設置します。航空機はそれぞれのアンテナから送信される電波によって誘導されます。電波の障害にならないよう、アンテナの前方には広いスペースを確保する必要があります(黄色い斜線のエリア)。この写真は2000年に神奈川県の横須賀沖に設置されたメガフロート(超大型浮体式構造物)空港のILSの評価試験を行った際のものです(今回の試験とは直接関係ありません)。
ILSの例です。左右方向、上下方向の誘導を行うシステムをそれぞれローカライザ(LLZ)、グライドスロープ(GS)と呼びます。LLZは滑走路の延長線上に、GSは滑走路の脇に設置します。航空機はそれぞれのアンテナから送信される電波によって誘導されます。電波の障害にならないよう、アンテナの前方には広いスペースを確保する必要があります(黄色い斜線のエリア)。この写真は2000年に神奈川県の横須賀沖に設置されたメガフロート(超大型浮体式構造物)空港のILSの評価試験を行った際のものです(今回の試験とは直接関係ありません)。
猛暑の今日、大樹町で騒音計測試験を実施していたMuPAL-εが調布へ帰ってきました。
MuPAL-εは7月26日から大樹町で騒音計測試験を行なった後、31日に大樹を出発、翌日の8月1日に帯広から青森、仙台を経て、浦安へ到着し、そのまま点検に入っていました。大樹に向けて調布を出発したのが7月25日ですから、約3週間ぶりの調布です。

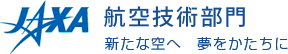



[このページを共有]