昨日コンテナから出され、再び梱包されたボナンザ。
晴天の今日、調布飛行場の敷地内にある整備工場に到着しました。
着陸レーダ用のアンテナは、ヘリのお腹、通常はMuPAL-ε用ドップラーレーダーが付いている場所に取り付けます。何本も出ているケーブルがひっかからないよう、ぶつけて傷を付けないよう、手塩にかけて育てたアンテナの扱いには細心の注意が必要です。機体に取り付けるところではネジで4箇所を仮止めするまで3人がかりでそぉっと持ち上げて支えます。仮止めが終わると電ドラ(=電動ドラえもんじゃなくてどら焼きの一種じゃなくて電気で動くドライバー)で残り22箇所のネジを締め、最後はトルクレンチを使って念入り確認します。

取り付けのためのフレームとレドーム。小さな○が並んでいるのがアンテナ(パッチアレイ)。
このアンテナの取り付けには、フレームの準備から取付完了まで約1時間かかります。せまい隙間にナットを差し込まなければならなかったり、機体の下に入って不自然な姿勢でネジ止めをしたり...何かと手間のかかる作業なのです。

こういう体勢に備えて(?)、Hさんは日頃から腹筋を鍛えています。
いよいよボナンザが日本へやってきました。
2006年の夏と秋、JAXAはアラスカのCAPSTONEに参加し、飛行実験を行ないました。
その際、JAXAの実証機として購入したボナンザが、海を渡ってとうとう日本に到着したのです。(2007/2/14他の実験用航空機レポート参照)
調布のハンガーで初めてMuPAL-εと対面したのは2003年10月10日でした。あれから約3年半が経ち、今回は4回目のフィールド試験です。
JAXA宇宙科学研究本部(http://www.isas.jaxa.jp)では5年前から月惑星探査機に搭載する着陸レーダを開発しています。着陸レーダは探査機が惑星表面に降りるために必要な航法センサの一つで、マイクロ波を使って探査機の速度と高度を測定するセンサです。
JAXAの実験用航空機は研究目的だけでなく、様々な用途に使用されています。そのような用途の一つとして、種子島宇宙センターから打上げられるH-IIAロケットの打上げ支援の可能性を調べるための実証飛行を行いました。
この目的は、打上げ前の上空にある氷結層を含む雲の状態を観測し、その情報を打上げに活用しようというもので、今回、H-IIAの打上げ時期ではありませんでしたが、実験用航空機により、どの程度の高度まで観測が可能かの実証を行うとともに、実際に雲の観測を行いました。

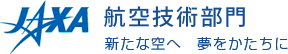



[このページを共有]