MuPAL-εは、この日は朝に調布飛行場を離陸し、有人機・無人機連携技術の飛行実験を実施した後、静岡へリポートに着陸しました。午後は、機体点検のために名古屋に移動します。このフライトを利用して、災害救援航空機情報共有ネットワーク(D-NET)の飛行実験が行われました。
2008/07/24付のレポートで有人機・無人機連携技術の予備実験の様子をご紹介しましたが、今回は実際にMuPAL-εと無人機が飛行中にデータ通信を行って、MuPAL-εの計器板に無人機の飛行状況を表示する実験です。
本実験は、ヤマハ発動機(株)との共同研究として実施しています。同社は、産業用無人機の開発・販売において世界有数の実績を有しています。今回の実験で使用した無人機は、同社が開発した産業用無人ヘリコプタで「自律航行型RMAX」と呼ばれる機体です。
実験場所は、同社が運用する無人機のテスト場で、静岡県掛川市にあります。無人機は、テスト場内を高度100ft(30m)以下で飛行します。MuPAL-εは、その上空を高度500ft(150m)以上で飛行します。無人機の飛行データをMuPAL-εに無線で送信し、ディスプレイに表示してパイロットが無人機の飛行状況を把握できることを確認するのが実験の目的です。
午前10時、無人機がテスト場に到着しました。専用のワンボックスカーで運び込まれ、組み立て、飛行準備があっという間に終わりました。

今月14日、クイーンエアでパイロットの全周囲映像撮影フライトを行いました。今日は機体を変えて、MuPAL-εで海上へ進出し、撮影を行いました。クイーンエアの場合と同じく海上で高度変更などを行うだけでなく、今度は海上でのホバリングも実施しました。

クイーンエアではコックピット中央に水平にしてカメラをおきましたが、MuPAL-εでは右席パイロットの右側に斜めにおいています。こうすることで、上から下まで窓のある部分を全て撮影することができます。

カメラの角度の都合で、MuPAL-εの場合は幸いにして後ろは写りませんでした。クイーンエアから撮影した映像とMuPAL-εから撮影した映像とを見比べると、あらためてヘリコプタと飛行機の視界の違いに驚かされます。
最後に周辺に目標物が多い状態でのホバリングの操縦を撮影するため、MuPAL-εで山間部へのフライトも実施しました。その結果撮影されたのが、14日の冒頭に掲載した写真です。
今回の一連のフライトはあくまで基礎データ集めであり、この後の解析が重要な作業となります。今後はさらに別の機体でも同じような撮影を行い、多様なデータを蓄積していくことで、視覚情報と操縦との関連について明らかにしていくことになります。
今回は、無線LANを使って航空機間でデータ通信を行う実験です。
無線LANは既に旅客機で使われ始めています。ただし、地上で駐機している状態で、運航会社のサーバにアクセスして情報をダウンロードする、という使われ方のみで、飛行中は使われません。無線LANは、他の航空機用通信機器に比べて安価で、無線免許が不要なため、導入が容易という利点があります。一方で、電波が微弱(10mW)なため、届く距離が短いのが欠点です。旅客機は高高度で機体同士が長い間隔をとって飛行するため、無線LANで地上や他の機体と通信することはできません。

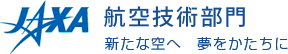




[このページを共有]